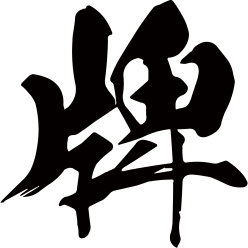雀鬼こと桜井章一氏の哲学に則った独特のルールがあることで有名な雀鬼会ですが、これまではあの有名な第一打字牌切り禁止くらいしか知りませんでした。
改めて興味が沸いたので、メディアから確認出来る限りの雀鬼会ルールについてまとめてみました。
AIで機械的に整理したので間違いがあるかも知れません。
index
雀鬼会ルール
全体を通してみると、何らかの理想に向けた合理を感じなくもないといったところかな(小泉構文気味)
感想を入れながら追っていきます。
基本ルール
ゲーム形式
東南戦30,000点持ちの30,000点返し。
ドラ
赤五筒2枚(常時ドラ)
和了条件
二家和は頭ハネ、三家和は流局。
カン
四つ目のカンは流局、四人立直時点で流局。
チョンボ
流局(例外あり)
点数
黒棒10本未満切り捨て、ハコ割れゲーム続行、流し満貫あり。
役
九種九牌倒牌なし、人和・数え役満は不採用、片和了り禁止、同巡内での食い替え禁止。

この辺までは意外にもハコ割れ続行以外は他のフリーで採用されているものに近い。数え役満は店によるかな。あと、持ち点あってるのかなこれ?
特定の打ち方に関する制限
- 一打目の字牌切り禁止(ただし、ダブリーで最終形の場合は除く)
- ドラは6巡目まではテンパイ以外で切ってはいけない
- 即引っかけリーチの禁止(ただし、ダブリーで最終形の場合は除く)

有名なやつですね〜。ダブリーのときはありなのか。
立直と和了
立直
見逃し、フリテン立直可。送りカン不可、テンパイが変わるカンは不可。
見せ牌
見せた牌の色全て出和了り不可(字牌は現物のみ)
和了放棄
空チー、空ポン、空和了り、チーロン、ポンロン、発声間違い、多牌、少牌、その他ペナルティ行為。
包(パオ)
大三元、大四喜を確定させる牌を鳴かれて和了られた場合は包(パオ)となる。
- ツモられた場合、鳴かせた者の一人責任払い
- 他家の振込みの場合、鳴かせた者と折半払い
- 鳴かせた者が振り込んだ場合は一人責任払い
カンの制限
- 原則として明槓は禁止。暗槓は面前テンパイ時と立直後に限られる
- 暗槓してのダマは認められないが、一手変わりの四暗刻は例外

これ面白いですね。無責任なカンが嫌いなので、標準化して欲しい(笑
点棒について
浮いた分は卓の右脇に上げる(積み棒はチップを代用)
誤フーロに関するルール
- 鳴く牌を間違ってさらした場合、局が進行していなければさらし直し、その色を見せ牌として続行
- 局が進んでしまった場合は和了り放棄のノーテン扱い(+ペナルティ)
特殊なルール
裸単騎
基本的に認めないが、役満の場合は例外。
捨て牌
捨て牌の背が河に触れたら戻すことは出来ない。
状況判断について
和了制限
南二局以降、点棒の少ない者が二人浮き及び三人浮きの状態を一人浮き状態にする和了りは不可。

複雑かつ、収支戦でこれは厳しい!
立直制限
大三元の牌のうち2牌鳴かれている時、四風牌2牌を鳴かれている時は立直不可。

変形のパオみたいなものですか。
暗槓のし忘れ
立直後、カンを出来る牌を自摸ってきたのに不注意でカンしなかった場合はペナルティ。
腰について
上家の切った牌を鳴こうとして一瞬動きを止めた場合、その牌が鳴ける牌ならその牌とスジの牌は出和了り不可。
ドラの早切り
聴牌前にドラを切り、それがポンされた場合、以後ツモ切り。ただし、役満の制約がある場合は例外
その他
- 持ち点が8,000点未満になる打ち方は禁止
- ペナルティは和了放棄+振り込み禁止

振り込み禁止というのはどういうことなのだろう?AIが間違えてる?
伝説的ローカルルールとしての存続
冒頭の繰り返しになりますが、くれぐれもこれはAIでまとめたものなので、間違いがあるかも知れません。
しかし難しい、これは難しい。たまにやってみるのは面白いかも知れないけど、私には無理だなー
昨今ではほとんど採用されることはないけど、クイタン後付け無しの、いわゆる「なしなしルール」や、連荘が5本場を越えると「二飜縛り」になるというルールもあったことだし、愛好家の間でこの雀鬼会ルールも存在し続けるのかも知れない。